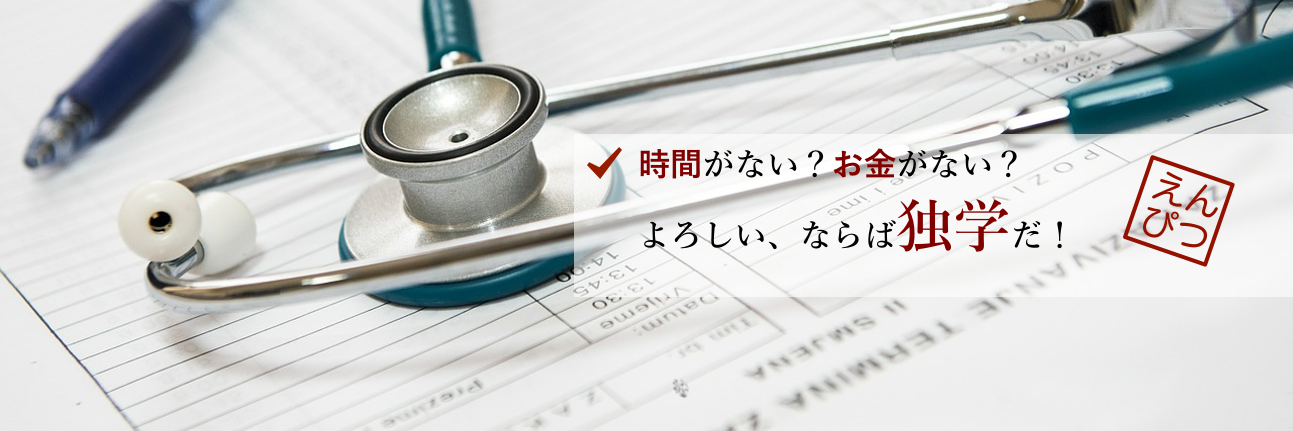皆さんこんにちは、えんぴつです。今回は東京大学医学研究科のHPより発見してきた研究について解説します。免疫システムに関わることなので、医学部の編入試験対策として有用だと思います。それではどうぞ!
まずは予備知識
今回の研究内容を理解する上で必要な予備知識を解説します。数が多いので、それぞれ個別に区切って説明していきます。
RANKLについて
別名RNAKリガンドと言います。RANKに結合する事によって効果を発揮します。破骨細胞の機能を亢進させ、骨の新陳代謝を促す役割を持っています。骨粗しょう症にかかると骨がボロボロになるということは知られていますが、この病気の治療の際にはRNAKとRANKLの結合を阻害する薬剤が投与される場合があるそうです。(weblio参照)リガンドの意味は分かりますか?これは医学部編入レベルの知識なので是非覚えておいてください。リガンドの意味については、当サイトでも紹介しているESSENTIALCELL BIOLOGYにも書いてあるので調べることを推奨します。
多発性硬化症について
多発性硬化症とは、脳や脊髄などの神経系に病巣ができ、様々な症状がでる病気だそうです。別名MSといい、Multiple(多発) Sclerosis(硬化)の頭文字をとっています。病巣において、脳や脊髄などを構成する神経細胞のミエリンが脱髄することが既に知られており、脱髄した神経細胞では神経における情報伝達がうまくいきません。つまり跳躍伝導がうまくいかないということです。跳躍伝導については、医学部編入レベルじゃなくても高校レベルの知識で知っている方が多いと思います(^^)。
「多発性硬化症.jp」より
患者数が世界全体で約250万人いるそうです。結構規模がでかいですね。なお、今のところ根治させることは難しい難病だそうです。脳神経が深刻な被害を受け、脳細胞が死んでしまえば、そこから回復させることはとても難しいことです。なぜなら、神経細胞は最終分化細胞であるため、それ以上増殖しないからです。このため、治療方法を見つけることが急務でした。治療方法を発見するためには、発症メカニズムを知る必要があります。今回この記事で紹介するのは、この発症メカニズムの一部が解明されたという趣旨の論文です。
血液脳関門とは?
医学部に向けて頑張って勉強をしている皆さんならば、「勉強の時はブドウ糖を取るのがいい。脳はブドウ糖以外はエネルギーとして受け付けないんだよ」というような事を聞いたことがあるかもしれません。えんぴつは高校生の頃に友達のお父さんに勧められて角砂糖状のブドウ糖を食べてみましたが…あんまり効果は感じられませんでした(^_^;)。
それはさておき、ブドウ糖しか受け付けないのは、脳をめぐる前に血液脳関門にてブロックされてしまうからです。この門は非常に厳しく、普段は自身の免疫細胞すら通しません。ちなみに、アルコールや麻薬は脂溶性なので、この関門を通過することが出来ます。
それでは本題
それでは、前知識を踏まえて本題に入ります。東京大学の研究グループは、多発性硬化症において、「本来超えられないはずの脳血液関門を免疫細胞が超えられるのはなぜか?」という部分に注目しました。そこで、多発性硬化症のようなものをマウスでも起こしてみてメカニズムの解明を試みました。すると、病原性T細胞がRANKLを発現し、これが炎症性細胞を脳血液関門内に呼び寄せ炎症が起こることがわかったそうです。
筆者たちは次に、比較実験をするために、T細胞だけでRANKL遺伝子を破壊したマウスを用意し実験しました。その結果、この病気の発症率も病態の進行も抑えられることが確認されました。
また、更に調べてみると、T細胞が発現するRANKLはアストロサイトに存在するRANKに結合することがわかりました。アストロサイト側のRANKを破壊した結果、発症率が抑えられたことからわかったみたいです。
そして、RANKLに対する低分子阻害剤を作用させてみたところ、発症率が低下したそうです。つまり、T細胞におけるRANKLとアストロサイトにおけるRANKの反応が多発性硬化症発症のキーになるかもしれない、ということがわかりました。
「東京大学 神経難病が起こる仕組みを解明」より 一部改変
いかがだったでしょうか?なぜ免疫細胞が脳血液関門を通過できるのか?という謎については、この研究を見る限りだと引き続き研究する必要がありそいうですね。ただ、通過するメカニズムがわからなくても、治療の糸口を見つけるのに重要な研究であることには間違いありません。人間ではまだ試していないようなので、今後臨床実験がなされそうですね。骨粗しょう症の薬として既に治療薬が存在するので、治験のハードルは比較的低いかもしれませんね。それでは今日はこの辺で(`・ω・´)ゞ
出典元:「多発性硬化症.jp」より URL:http://www.tahatuseikoukasyo.jp/what/p01.html
出典元:「東京大学 神経難病が起こる仕組みを解明」より URL:http://www.m.u-tokyo.ac.jp/news/admin/release_20151209.pdf
出典元:「大阪大学 局所的な神経の活性が、病原T細胞の血液脳関門の通過ゲートを形成する。」より URL:http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/gcoe/jp/events/achievement/t/
出典元:「ナオルコム 血液脳関門」より URL:http://www.naoru.com/ketuekinoukannmon.htm
出典元:「weblio RANKL」より URL:http://www.weblio.jp/content/RANKL